ナノポアを使って細菌性髄膜炎の迅速診断 最速だと5時間で病原菌特定
この論文は2019年の9月にInternational Journal of Medical Microbiologyで発表された最新の論文です。
Rapid diagnosis of bacterial meningitis by nanopore 16S amplicon sequencing: A pilot study

世界最小DNA解析機 MioION
最近、オーストラリアでは、髄膜炎菌の最新技術のワクチンの登場により、髄膜炎菌の感染が激減しましたが、5から10年前くらいまでは、髄膜炎菌の感染で、時々、赤ちゃんや若者がお亡くなりになったりしました。オーストラリアだと、頭が痛いと、なんでもかんでも鎮痛消炎剤のパナドールというのを若者とか飲んで済ませてしまうのですが、たまに、そういう若者が髄膜炎で亡くなってしまいます。もし、医者に診てもらって、抗生物質を飲んでれば助かったと思われます。病原体の迅速な特定や細菌性髄膜炎の明確な診断が重要なのは明白です。

オックスフォード・ナノポアテクノロジーズ MinION 約10万円
今日ご紹介するのは、度々、私のブログに出てくる小型のDNA解析機 オックスフォード ナノポア社のMinIONが細菌性髄膜炎の迅速診断を可能にするという話です。最速だと5時間で病原菌特定が可能です。
病原体の迅速な同定は、細菌性だけでなく髄膜炎の原因の診断に役立ち、医者は、これまでのような経験だけの診断でなく、カスタマイズされた抗生物質治療を行うことができると予想されます。
重篤な髄膜炎は、赤ちゃんや、時々若者でも命を落としかねず、運が悪いと感染してから、悪くなるのが早いので、検査結果がすぐに出るのは、患者さんにとってのメリットはかなり大きいです。
実験の内容
この研究では8つ症例を対象に、細菌性髄膜炎の患者さんの脳脊髄液(CSF)サンプルが実験に使用されました。DNAを脳脊髄液から抽出し、16SリボソームDNAをPCRを使って増やします。そして、MinIONを使ってDNA解析を最大3時間実行しました。読み取ったDNAのデータは細菌データベース使って分析され、結果は従来の細菌を培養して細菌を同定した方法と比較しました。
[aside]補足 16SリボソームDNA
細菌の中の16SリボソームDNA遺伝子(正式には16SリボゾームRNA遺伝子)を調べます。この遺伝子は生命維持に重要な遺伝子なので、すべての細菌に存在していますが、細菌の種類によって、ちょっとづつ遺伝子のDNAの配列に違いがあります(SNPsの事です)。その違いを利用して、サンプルのDNAの16SリボゾームDNA遺伝子たちを解析すると、どんな細菌がどれくらいいたかわかることができます。現在の最新技術なら、細菌の種類とどのくらいサンプルに含まれているかまで分かります。 [/aside]
[aside]補足 16Sシーケンス
細菌の中の16SリボソームDNA遺伝子(正式には16SリボゾームRNA遺伝子)のDNA配列を解読する事 [/aside]
[aside]補足 PCR
DNAの特定場所だけをひたすら増やせる機械[/aside]
Conventional Diagnostic Testは、従来のように、サンプルの中にいる細菌を培養して、結果を出します。約2日から7日かかります。Nanoporeの方は、文字どうりナノポアを使った場合の工程です。最短で5時間です。 参考資料:オックスフォード ナノポア社
結果
すべてのケースで、脳脊髄液から病原菌が正常に特定されました。 16Sシーケンスは、従来の診断テストよりも感度が高く、抗生物質で処理したサンプルでも適切に機能しました。 MinIONシーケンスにより、所要時間は、従来の方法(2-7日)に比べ、大幅に短縮され(最短5時間)、特定のケースでは10分のシーケンスでも病原体検出に十分でした。[voice icon=”https://dnanohanashi.com/wp-content/uploads/2019/09/blanc_20190906_201628-300×293.png” name=”DNAパパ” type=”r”]10分はシーケンスだけです。すべての工程は最短で5時間です。”抗生物質で処理したサンプルでも適切に機能しました。” この意味は、抗生物質を使うと、血液中の細菌が死んでしまい、従来の方法のように細菌を培養する検査法では、細菌を特定できない事がありました。その反面、DNA検査は、細菌が死んでも関係ないです。[/voice]
まとめ
すべての工程は最短で5時間ですが、DNA解析に、たった10分しかかからないのは驚きです。私の同僚が、この分野の研究をしていますが、実際には、ナノポアの場合は、DNAをリアルタイムで解析できるので、1-2分でも細菌の種類を特定可能だそうです。
ほとんどの時間は、DNAの解読前の下準備にかかっていまして、だいたい約3時間くらいかかってます。この部分が、どれだけ早くなれるかが今後の鍵です。
下準備が必要な理由は、血液中の、ヒトの細胞(白血球等)やヒトのDNAを取り除く為です。そうしないと細菌以外の余計なDNAの情報ばかりシーケンスされて非効率的だからです。
将来的には、血液中の病原体をかなりの短時間で、特定する事が可能と思います。
最終的に、細菌性髄膜炎の明確な診断が短時間でできるようになるでしょう。そして、多くの患者さんが、助かることを願います。
[voice icon=”https://dnanohanashi.com/wp-content/uploads/2019/09/blanc_20190906_201628-300×293.png” name=”DNAパパ” type=”r”]近い将来に血液のようなサンプル採取から結果が出るまでに、一時間以内にできるようになると思います。[/voice]
参考文献:
Rapid diagnosis of bacterial meningitis by nanopore 16S amplicon sequencing: A pilot study
Jangsup Moon, Narae Kim, Tae-Joon Kim, Jin-Sun Jun, Han Sang Lee, Hye-Rim Shin, Soon-Tae Lee, Keun-Hwa Jung, Kyung-Il Park, Ki-Young Jung, Manho Kim, Sang Kun Lee, Kon Chu.

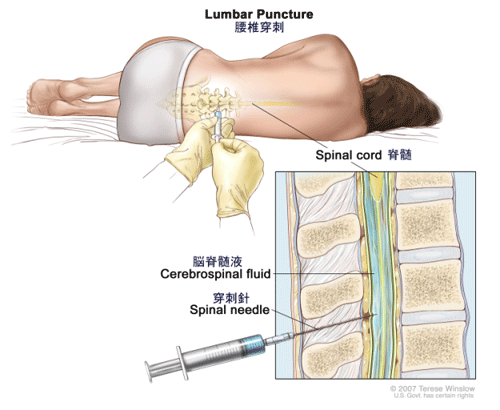



コメント